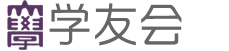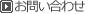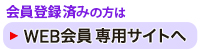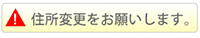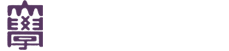OB・OGの活躍
会報に載せきれなかった鈴木源一さんの近況報告!
1.中央学院大学の学校経営は間違っていません。歴史が証明しています。
私は53年商学部の卒業生ですが、私がいたころは、商学部のみの単科大学でした。
今や大学院、商学部、法学部、現代教養学部など総合大学です。
40年でこんなに発展するとは思ってもいませんでした。
今も覚えています。
税法・商業科教育の上平先生、経済原論の松本先生、東洋史の井出先生、産業心理学の高木先生、産業概論の
川部先生など大変お世話になりました。川部先生の授業は面白く、ぐいぐい引っ張られました。
日本の産業は川上と川下で出来ている。
なんのことかよく解らなかったのですが、聞いていると、製造業と消費者の間に一次問屋、二次問屋があって
利益を得ている。
今で言えば有名百貨店とスーパーです。ユニクロやワークマン、セブンイレブンやローソンです。
40年前にすでにこのことを講義されていました。
上平先生に公務員試験を受けたいのですがどこが良いかと聞いたら、「受けられるのならすべて受けてみな
さい!」と。
可能性を試してみたら?と理解しました。
そのことが忘れられず、卒業してから東京都大卒試験を受け、合格することができました。
上平先生のおかげです。
今日この頃は、学生の要望に応え、公務員合格100人企画など、いろいろと企画されています。
社会が大学に何を求めているか、先人の先見性がこれに応えていたからこそ学生が集まってきたと思われ
ます。
2.社会の少子高齢化について
社会は少子高齢化で、どの大学も優秀な学生を集めるのに苦労しています。先が読めない社会です。
東京オリンピック後の日本経済はどうなるのか。厳しい時代が来るのか、どうか。
こんな先が読めない社会だからこそ、公務員人気があるのではないでしょうか。
3.なんとも寂しい
僭越ながら、私は大学を卒業する時に千葉県の消防大卒試験に合格しました。また、その後東京都の試験にも
合格をし、東京都庁金融部・商工部・雇用就業部で仕事をしてきました。
今は定年退職をし、東京都再任用職員として働いています。
今日この頃思うのは、このままだと東京都庁に中央学院大学の卒業生が居なくなることが何とも寂しいです。
中央学院大学の学生を都庁に入れたい。そうでないと中央学院大学のDNAがなくなってしまいます。
私は中央学院大学の卒業生です。後輩に道を譲りたい。
合格するには大学のゼミ形式で、皆で切磋琢磨するのが効果的です。
やれば、警視庁・東京消防庁・東京都行政職などの試験に受かります。
そのためには試験に合格した経験の有る人が、ゼミ形式で教えるのが効果的だと思います。
中央学院の学生は優秀である!
千葉大や中央大もいいけれど、中央学院大学もあなどれない。そうなることを願っている一人です。
僭越ながら以上をもちまして、近況報告に代えさせていただきます。
ありがとうございました。
1978年商学部卒業 鈴木 源一
河元智行さん(まくら株式会社代表取締役)
ネットでまくらが売れるわけがない!そんな常識を覆した注目の企業家。

まくらのネット通販でいま話題の会社がある。その名も「まくら株式会社」。何ともストレートな社名のこの会社を経営するのが、本学商学部OBの河元智行さんである。
起業の背景、その経営方針、大学時代の思い出などを語っていただいた。
まくらは自分のいつもの布団で試さないとわからない!
熾烈なネット通販界で、まくらだけで勝負し成長を続けるまくら株式会社。
取り扱うまくらの点数は約800点、直営で18もの通販サイトを運営する。
まくらに特化した展開の背景には、河元さん自身の苦い経験があったという。
「20代の頃、いろんな枕を買って試したが、自分に合うものが見つけられず、逆に首を痛めることになってしまって」。
そのとき、達した結論が「まくらは自分の布団で寝て試さないと、わからない!」ということ。そうした経験をもとに同じ悩みを抱える人がいるだろうと、まくらの情報ポータルサイトを自ら立ち上げたところ、人気サイトに。サイトの掲示板に多くの人が集まり、寝具メーカーからもリリース情報が寄せられようになった。その年(2003年)のニフティ「ホームページグランプリ」で準優勝。この賞金を元手に起業に踏み切った。
“インターネットでまくらが売れるわけがない! お店で触ってみないとわからないはず”。そんな世間の常識こそ、河元さんの勝算だったいう。
「お店で触っただけでは絶対にわからない。実際に寝てみないと。家で寝てみて合わなければ、返品してもらって構いません」。
20日間有効の返品サービス。割引なしの定価販売。在庫レス。創業以来、この3つを崩さない。「“安眠”の前に“安心”を売ること」。それが、まくら株式会社が提供する付加価値であり、成長の原動力だ。
創業当時は銀行に融資の相談に行っても、まったく相手にされなかったと笑う河元さん。
「まだまだ成長段階。もっとまくらでできることがあるはずです。まくらバカですからね、私(笑)」。
“我孫子”がつないだ3代にわたるネット通販会社の起業
 <大学時代は勉学よりも、アルバイトとサークル活動に明け暮れたという河元さん。「唯一、授業で覚えているのは椎名先生の『財務諸表論』ですね」。
<大学時代は勉学よりも、アルバイトとサークル活動に明け暮れたという河元さん。「唯一、授業で覚えているのは椎名先生の『財務諸表論』ですね」。
測量のアルバイトは時給が高かったこともあって、熱心に続けていたという。このアルバイトで不動産のことを知り、独学で宅地取引士資格を取得した。
「お世辞にも大学で勉強したとはいえませんが、アルバイトやサークルでの交友関係や出来事をとおして、自分から『知りたい』という知識欲が出てきました。やらされるのではなく、経験の中から必要を感じて、自ら学ぶことの大切さに気づくことができたと思います」。
我孫子市寿で創業したが、実はこの場所は学生時代に世話になった測量会社の2階で、オーナーのその測量会社が家賃2万円で貸してくれた。この地にまつわる面白いエピソードがある。
順調に売り上げを伸ばし、社員も10名を超えた頃、さすがにこの場所が手狭になり、我孫子市東我孫子に移転。このとき、社員の一人が「自分はここに残って、お風呂グッズの通販サイトを立ち上げる」と起業。さらにその通販サイトも順調に成長し移転。このとき、また社員の一人が「自分はここに残って、キッチン用品の通販サイトを立ち上げる」と起業したという。測量会社の2階から3代続けてネット通販会社が立ち上がった。
「“我孫子”という字は、『我』『子』『孫』の3代なんですよね。この地から3代にわたって起業したのは感慨深いですね」。
まさに我孫子の「トキワ荘」。ちなみにこの3代にわたる物語は、11月に中央学院大学で講演する予定だ。
22世紀のまくらに向け気づきをビジネスに変える

まくら株式会社の特長は、極力、在庫もたないことだ。注文が入ってから、メーカーに発注を出し、納品され次第、お客さんに発送する流れだ。無駄な在庫を減らすことで、在庫処分の割引セールをやる必要がない。
「無駄な在庫、無駄な売り上げをあげないことが鉄則。お金もなくスタートした会社なので、確実にキャッシュがまわるやり方を模索しました」。
早い時期から社内にシステム開発部門を設けたのも、河元さん流の経営術だ。それまで売り上げが伸び、業務量が増えるたびに社員を増やしてきた。しかし、忙しさは変わらなかった。
「マンパワー頼りではいつまでも変わらない。自動化できる部分は極力自動化して、人がやる仕事を減らしていこうと」。
社内の業務システム開発のためにプログラマーを雇い入れ、業務の効率化に取り組んだ。現在、社内で稼働している業務ツールは133種類に及ぶという。中でも自動予測発注システムは、在庫レス経営の肝となるシステムである。他のネット通販会社にも評判となり、ASPサービスとして、現在、180社に提供している。経済産業省の「IT経営力大賞2012」の優秀賞も受賞した。
創業以来、増収黒字を続ける河元さん。創業時は銀行に融資を断られた。軌道に乗り始めた頃、取り込み詐欺に遭った。主力取引先メーカーが廃業したこともあった。
「でも、振り返ると、そうしたことに面白みがあって、自分にとって力になったと思えます」。
気づきをビジネスに変える。これこそが起業家に求められる力だ。
“まくらバカ”を公言する河元さん。
「まくらは、人間に睡眠する習慣があるかぎり、なくならないはずです。100年経ってもあるはず。まくらは、目鼻口耳がある人間の一等地に一番近いところにあるアイテムです。22世紀のまくらは、朝起きたら、その日の予定を教えてくれたり、情報のプラットフォームになっているかもしれません。ワクワクしますね」。
●プロフィール
まくら株式会社 代表取締役。1975年我孫子市生まれ。我孫子生まれの我孫子育ち。高校時代はオリジナルで選曲したオムニバステープを作り、クラスメイトや先生、他校の生徒に販売。その売上金で予備校に通い、中央学院大学へ。2004年、まくら株式会社を設立、2012年、経済産業省「IT経営力大賞2012」優秀賞受賞。現在、18店舗運営。
長尾治人さん (株式会社とんでん 代表取締役社長)
椎名前学長との出会いが生き方を知るきっかけに。
 北海道生まれの和食レストランのチェーン店として、いまや関東でも95店舗を展開する「とんでん」。
北海道生まれの和食レストランのチェーン店として、いまや関東でも95店舗を展開する「とんでん」。
家族3世代が楽しめる豊富な和食メニューが魅力で、一度は利用された方もいらっしゃるのでは。
同社の社長として8年前から経営の舵を執るのが商学部OBの長尾治人さんだ。父・治氏が創業し、小さい頃から経営者への道を嘱望された長尾さん。しかし、青年時代は家業を継ぐことに抵抗があり、父への反発心もあったと振り返る。
「へそ曲がりだから(笑)、父の会社には興味なかったですね。理数系が好きで、大学も本当は東京理科大に行きたかった(笑)」。
中央学院大学に入学したのも、まずは北海道を出るため。「父の目から逃れて、隠れて勉強して翌年、東京理科大を受験しようと本気で思っていました」。
そんな長尾さんが、半ばしぶしぶ通った中央学院大学のプレゼミで出会ったのが椎名市郎前学長だった。その1回目の授業を長尾さんは今でも鮮明に覚えている。
「『天に唾しても、自分にかかるだけだ!』と言って、いきなり上を向いて唾を吐いて、本当に自分の顔で受けたんです。すごい先生が大学にはいるなと(笑)。と同時に目が覚めた気がして」。
強烈な出会いに惹かれ、以後、研究室にもときどき遊びに行くように。
「研究室に行くと、本のリストを紙に書いて渡してくださって。『お前に本をあげても読まないだろうから、このリストの中の本を買って読め』と(笑)。『第三の波』や『東京裁判』など、いろいろ読みました」。
いつしか理科大受験の計画は消え、経営研究室にも所属し、独学で財務も勉強した。
「2年、3年のときはとにかく真面目に勉強しましたね。5限までびっしり履修して、全科目とも一番前に座って、ほとんど皆勤賞。あのとき椎名先生との出会いがなかったら、そうはならなかったと思います。今でも何かの問題に直面して、判断しなければならないときに先生の『天に唾する』という言葉が蘇ります。誰か陥れようとしても、必ず自分に戻ってくる。生き方を教わったこの言葉との出会いに今でも感謝しています」
飲食は文化。とんでんの文化を守るため社長に就任。
札幌出身の長尾さんは、“関東の夏”に苦労した思い出も。
「もう、暑くて(笑)。最初は柏のアパートに住んでいたのですが、通うだけでもしんどくて。2年次から我孫子に引っ越しました。大学に近くなった分、真面目に勉強するようになりました。休講のときもウチに帰らず、図書館で自習していました。当時、学食はまだプレハブでしたけど、図書館は新しくて冷房完備。よく利用していました」。
経営研究室では、顧問だった故・生田富夫元学長に酔って絡んだという逸話も。
「同期が4人居て、僕以外みんなお酒が弱くて。それでも先輩たちが勧めるものだから、『僕が代わりにみんなの分を飲みます!』と言ってしまって(笑)。大瓶ビール1ケースを空けたところで無事解放されたんですけど、その後で生田先生に散々グダ巻いたらしくて(笑)。全然覚えてないですけど」
恩師との数々のエピソードを懐かしそうに語る長尾さん。かけがえのない青春の1ページが確かに中央学院大学で刻まれている。
現在、社員665名、パートを含め約6,000名の従業員を抱える経営トップ。8年前に社長に就任したが、それまでは頑に断り続けていたという。父が人生を賭けて築き上げた会社。果たして自分が切り盛りできるのだろうか。そんな不安もあった。
「あるとき親父が『お前が継がないなら、会社を売る』と言い出して・・・。飲食はひとつの文化ですから、誰かの手に渡れば文化も変わってしまいます。そこで一番苦労するのは従業員たちです。それはできない「じゃあ、やります」と。
幹部会議で社長就任の挨拶をした日も印象的だった。
「いわゆる型通りの挨拶だったのですが、僕が席に戻るまで、幹部クラスがみんな立ったまま、ずっと拍手をしてくれていて。そのとき、『もう、逃げている場合じゃない。この人たちのために死ぬ気で頑張ろう!』と誓いました」
従業員の笑顔に救われた夜。先人への感謝を胸にさらなる発展へ
意を決し社長に就任した2年後、あのリーマンショックが起こる。同業他社の店も客足が途端に減った。長尾さんは資金繰りに奔走した。当時、新規出店も重なり、年間50億円の資金が必要だったという。金融機関を駆け回り、頭を下げ、資金を集めるものの、到底足りない。「もう駄目だ」と半ば覚悟したある夜のこと。
「疲れ果てて社に戻ると、併設する店舗の窓際の席にお客さんがびっしり埋まっているんです。そこに従業員が元気に応対している姿が窓越しに見えた。あの笑顔に本当に救われましたね」
お客さんのために生き生きと働くその姿に勇気づけられ、その後、いくつかの銀行から融資を取り付け、予定額を調達したという。
「会議ではキツいことも言ったりしますが、ここだけの話、僕は従業員にはまったく頭が上がらないんですよ(笑)」
和食の強みを活かしたおせち料理の受注も好調で、ここ数年、52,200食を完売しているという。また、海外へも目を向け、現在、ロシア出店を準備中だ。
経営者たる者は、ときに決断を迫られるが、長尾さんは何かを決めるとき、自問自答を繰り返すという。
「物心つく頃から“社長の息子”として周囲に育てられ、会社でも立場ができてくると、周りは何も言わなくなります。ですから、会社で右と言ったら、ウチに帰って左だと考えてみる。その繰り返しです」
誰のせいにするのでなく、自分と真剣に向き合うことで、最適な答えを導き出す。
「最後は自分の責任に置き換えないと、次の行動は起こせませんから」
若かりし頃、反発した父の会社。いま長尾さんは経営者として着実に歩みを進めている。
「先代や先輩たちが築いたいまに感謝しながら、いまある苦しみを乗り越える努力を惜しまないこと。この真摯な想いこそが、一歩先へとまた進むための大きな力です」

●プロフィール
株式会社とんでん 代表取締役社長。
父・治氏が北海道・札幌市で1968年に創業し、8年前から社長に就任。
『大衆の中により深く 豊かで楽しい生活の提供』を経営理念に関東95店舗、北海道18店舗、日帰り温浴施設(北海道札幌市)を展開。
今後はロシアへの和食レストラン展開も計画中。
会報には載せきれなった武井壮さんのインタービュー!!
本学卒業生で現在活躍中の武井壮さんにインタビューしてきました。
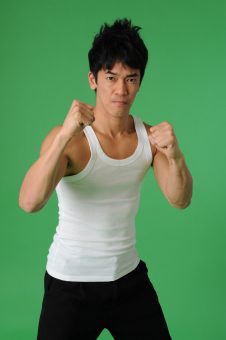
学友会会報にもインタビューの一部を掲載させていただきましたが、載せきれなかった記事がまだまだあります。
是非下記のインタビューから武井さんの努力やポリシーを感じていただけたらと思います。
◆武井壮さん インタビュー◆
【生きるための「宝物」を掴んだ場所。】
「陸上・十種競技元日本チャンピオン」という身体能力の高さと「百獣の王」をめざす特異なキャラクターが受け、アスリートタレントとして現在、人気沸騰中の武井壮さん。2013年上半期メディア露出度第3位、ご存知の方も多いのでは。
陸上競技を始めたのは何と大学から。神戸学院大在学中に十種競技で頭角を現し、当時、日本陸連の強化部長だった本学・小林敬和現教授の目にとまり中央学院大学に3年次学士入学。
「『2年間で日本一になる』と決めていたので、アルバイトも遊びも一切やらず、毎日トレーニングばかりやっていました」。
恩師・小林先生との思い出は「とにかく合宿の練習メニューが半端じゃない (笑)。国内トップクラスの猛者が合宿初日からボロボロになるんです。でも、それをきっちりやり切ると、フィジカルがしっかり強くなる。どのタイミングでどこを鍛えればいいか。そのさじ加減が絶妙でした」と振り返る。
日本一という明確な目標を定めた2年間。当時は十種競技の上位の選手層も厚かった。
「『これで本当に勝てるのか?』。毎日が不安でした。それを打ち消すために毎晩、夜中に356号線を走っていました。東我孫子駅の近くの上り坂を足がヨレヨレになるまで走って。そこで初めて『今日はやることやった』と安心して眠ることができました」。
そして1997年、4年生のとき出場した日本陸上選手権で念願の優勝。100m走ベストの10秒54は、2013年現在も破られていない日本最高記録。
「僕にとって中央学院大での2年間は、文字どおり24時間を陸上に捧げた、濃密な時間でした。身体能力が最も早く高まった時期で、日本タイトルも獲れました。陸上以外にも教職免許を社会科と商業科の2つも取得できましたし、たくさんの宝物をもらったキャンパスです」。
【異例のスピードで日本一に上り詰めたその秘密は!?】
十種競技を始めたのは神戸学院大の3年生のとき。当時流行していた漫画『デカスロン』の影響も大きかったと語る武井さん。だが、競技を始めてわずか3年足らずで日本一に上り詰めた。
「1年目で7,000点、2年目で7,300点台、そして3年目に7,606点で日本一。当時の十種競技界にとっても異例のスピードだったみたいで、『武井壮って何者なんだ』って言われていました(笑)」。
しかし、そこにはしっかりとした戦略があった。十種競技は2日間にわたって行われる。1日目に100m、走幅跳び、砲丸投げ、走高跳び、400m、2日目に110mハードル、円盤投げ、棒高跳び、やり投げ、1,500m。
「十種目中、七種目は“走る”んです。じゃあ、スプリント力を上げれば、7種目伸びるじゃないかと」。
当時の日本選手は円盤投げ、砲丸投げといった投てきで得点を重ねる選手が多かった。その頃、日本選手権7連覇を続けていた金子宗弘選手も投てきを得意としていた。
そんな中、「走るスピード、そして何本走っても疲れない体力づくり」に特化してトレーニングを積んだという。
「技術練習はほとんどしなかったですね。フィジカルトレーニングばかり。思った通りに身体を動かせるための練習です。それがあれば技術は真似するだけでいい」。
トレーニング中心の毎日。もっぱら授業中は身体を温め、体力回復の時間に充てたという。
結果、金子選手の8連覇を阻止して、武井さんは狙いどおりに日本一を獲った。まさにそれまでの十種種目の歴史を変えた勝ち方だった。
「フィジカルが高まったときが僕の記録なんです」。
これは今日まで続く武井さんのトレーニング理論である。つまり、こういうことだ。
「例えば、高跳びならば、バーを超えられればいいわけで、どんな跳び方でもいいんです。1回飛べれば、飛べるわけですから、その飛ぶ力を強めていけば、当然、高さも上がってくる」。
シンプルで余計なことをしない。ときにアスリートは技術練習に走りがちである。思ったときに体をコントロールできるフィジカルを手に入れること。それが、武井さんがめざすアスリート像だ。
【人生の4年間はそんな軽いものじゃないはず。】
「僕にとって大学は宝箱みたいなもの。箱を開けると、いろんな分野の専門家がいて、社会とつながるパイプを持っている。知識も得られるし、コミュニケーションの輪も作ってくれる。一生応援してくれるような人間関係を作れる場所です。設備も世界的にトップレベルの設備が何でも揃っている宝箱です」。
それなのに“お宝”に気づかずに卒業してしまう学生が多いのではと武井さんは嘆く。
「僕はどれだけいっぱいの宝を引っ張り出せるかを考えていました。大学で得られる知識やつながりは、社会に出てなかなか簡単には手に入らないもの。そのスペシャリストがたくさんいるわけですから、もったいない。人生の4年間はそんなに軽いものじゃないはず。僕みたいに日本一にもなれる。それをもとに有名になることもできます。自分から取りに行けば、いろんなことをスタートできるところ。その鍵を掴む4年間にしてほしい」
そうすれば、好きでもない会社に就職して、やりたくない仕事に就くこともないという。
「社会から必要とされる能力を手に入れる時間が大学生活。そして社会が必要とするような逞しい人材を育てるのが大学の役目です。そんなやる気に満ちた学生と魅力ある先生が新しい未来を創るはず」。
毎日、自分史上最高でいること。昨日よりプラス1が、武井さんのポリシーだ。
「今日より昨日が楽しかったなんて寂しいじゃないですか。昨日より楽しい一日を送るためには、自分から進まないと」。
10月末にブラジルで行われる「世界マスターズ陸上競技選手権大会」100m種目に出場する予定だ。忙しいタレント業の傍らでは練習時間も十分に取れないのでは。
「いや、仕事終わって、トレーニングすればいいだけです。仕事を目一杯楽しんで、トレーニングも一生懸命する。それが、武井壮の仕事ですから」。
大学卒業後、40歳を迎えた今だからこそ、チャレンジする意味がある。きっと、また新しい成長の鍵を見つけるに違いない。
(2013年8月28日インタビュー)
◆プロフィール◆
陸上競技・十種競技の元日本チャンピオン。十種競技で数々の国内タイトルを獲得し(十種競技の100mのベスト10秒54は今も破られない日本最高記録)、独自の『パーフェクトボディーコントロール』理論をもって、ゴルフ・野球・ボクシング・陸上・柔道などさまざまなスポーツにチャレンジし続け、いまもなお、地上最強の百獣の王をめざして日夜トレーニングを続けている。
Twitterアカウント:@sosotakei
【硬式野球部】本学卒業生が日本代表に選出されました!
10月6日~14日(中国)の日程で開催される「第6回東アジア大会」の日本代表選手(24名)に、
本学硬式野球部42期卒業の秋吉 亮(パナソニック)が選出されました。活躍を期待しています。
OBの皆様、ご声援宜しくお願いいたします!